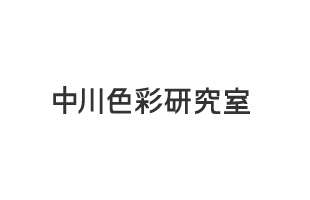中川ケミカルとDIC
それぞれの色の取り組み
流 麻二果(以下流):今日は「日本の色」というプロジェクトを立ち上げたのをきっかけに、色を仕事にしている方と画家である私が垣根を越えて色について話をできたらと思っています。
私は油絵を中心に創作をしていますが、作品を生み出していくなかで、色彩の監修など色にまつわる仕事が自然と増えてきています。そういった仕事の際に「日本の色を使ってください」という依頼をいただくことがあり、DICの伝統色の色見本を見ながら考える機会が多いのです。私自身も日本の伝統色はとても素晴らしいと感じ、好んでいますが「平成の今、なぜ私は平安時代の色を選んでいるのか」という疑問が湧いてきたんです。今の日本の色を考えるべきだと思い、このプロジェクトが始まりました。さまざまなフィールドで活躍する方のインタビューを掲載するウェブサイトが11月22日にローンチしたので、今回はウェブサイトの母体となる中川ケミカルの中川さんと、色の業界の第一線で活躍し、色のトレンドもよくご存知な周さんにも「日本の色」についてお聞きしたいと思っています。


中川 興一(以下中川):弊社は当初、中川堂という内装や看板の製作をしていた会社の開発部門としてスタートしました。現会長である私の父が塗料に代わる材料、カッティングシートの開発をスタートし、全国にある看板屋にこの新しい材料を提供する仕事を作りあげたのです。その後、株式会社中川ケミカルとして分離独立し、現在に至ります。切って貼れる、色斑や刷毛斑もないということで、急速に町の景色に広がっていったんですね。しかし、塗料と一個だけ違うところがあり(正確にはもっとありますが)、塗料は自由に無限大に現場でもどこでも色を作ることができますが、カッティングシートはあらかじめ色を決めておかなければならない。ある色の中から選んでもらうという工程が必要なんですね。そこで、さまざまな色のニーズに応えるために色彩研究を始め、「NOCS(Nakagawa Original Color System)」 を完成させました。
今では、カッティングシートだけではなく、色そのものを仕事にすべく「色で世の中に貢献したい」をモットーに事業を展開しています。10年くらいに前に、平社員だった私が役職をもらって本社に帰ってきた時に「色の世界共通言語、世界スタンダードを作りたい」という大きな目標を立てました。今では、NOCSは日本はもちろん、アメリカや中国、インドに広がっています。これがもっともっと広がっていけば色で世の中に貢献できるのかなと。あと5年くらいで世界のスタンダードが確立できたらいいなと思っています。
流:『アジアカラートレンドブック』の編集長も務められている周さん、DICの色の取り組みもお話いただければと思います。
周 昕(シュウ・シン)(以下周):私が所属しているDICカラーデザインというのは、2000年にできたカラーを主軸にした子会社会社で、カラーのスペシャリストが在籍しています。50年前から発行されている『DICカラーガイド』 をベースに、色のノウハウを使ってグッズの開発や、カラーコンサルティング、カラーデザインの仕事を提供しています。また、2008年から『アジアカラートレンドブック』を年1回発行して、アジアの色トレンドカラーとして毎年48色を提案しています。DICのカラーシステムから選ぶものもあれば、オリジナルで開発したものなどを盛り込んでいますね。常に色を見続けていると、色というのは生きているものだということを強く感じています。これは伝統色であっても、生まれたときには本当に生き生きした色だったはずで、その色を伝えていくためには、私たちがある意味仕掛けていかないといけないと思っています。伝統からトレンドの発信まで、流さんはアーティストとして、中川ケミカルさんは街づくりの第一線で、私たちは素材やデザインの提供というように、立場が違いながらも、日本の伝統色に限らず、色を発信していけたらと思っていますね。
中川:色が生きているというのは本当にそうだと思いますね。色は生まれた瞬間から変わっていて、それに色を見る側の感覚や価値観も変わっていくので、ずっと同じ色であり続けることはないと思うんですよね。だから色に携わる我々は色について考え続けることが大事だと思いますね。


日本が培ってきた色
海外から、現代から見ると
流:西洋の色は動物から、日本の色は植物や自然の中から生まれたという説があります。日本の色の原点である伝統色には時間や歴史、見ている人の感情も投影しているような感覚がありますよね。
中川:カッティングシートの色の選定は、田中一光先生、原研哉先生にお願いしたのですが、 やはりそこに日本人ならではの感性が入ってるんですよね。
流:本サイトではそれぞれの仕事や人生経験を踏まえお話いただいているのですが、考古学者の飯塚文枝さんが「伝統色は江戸と京都の色で、残っている色は京都の雅の中と江戸の町民のなかで根付いた色である」と。地方の色がまったく拾われていない、地域格差があるんですよね。私にとっては盲点だったのですが、確かに南北に長いこの日本だと地域によって気候や食べ物に違いが出るので、生活に大きな差があるんですよね。となると、地域に根付いていた色はもっとあったはずで、DICさんが現在取り組んでいらっしゃる地域に根ざした伝統色を掘り起こすプロジェクトはとても面白いなと感じました。
周:今のところ名古屋と兵庫県の伝統色をリサーチしました。地域の職人さんや神主さんなど、その土地に暮らし、伝統を受け継ぎ、リアルにその土地の色を繋げてきた方からお話を聞いて、編集しています。流さんがおっしゃったように、伝統色として定着しているのは貴族であったり一流の職人さんが仕上げた、完成させた色がほとんどです。だから、地元では親しまれているものであっても全国的に認知されていないものもあったりするので、根気強くリサーチしていかないと体系化するのは難しいです。
流:国での差はあるのでしょうか?
周:『DICカラーガイド』は日本、フランス、中国の伝統色を作成していますが、国の差、特徴がすごくありますね。中国は鉱物とか色材の産出国で、シルクロードの真ん中で西洋からもたらされた影響、そして大陸ならではの民族の数の多さが特徴として出るので、鉱物や絵具、建築装飾の色名が多いんです。フランスは人種の違いや多様性を感じさせるもの、髪の毛、眼、肌など。そのほかよく焼けたパン、夕焼けの色とか、ロマンチックな絵や詩に描かれたような美しい表現につながっている色名が多いのです。日本は繊細で職人技を感じさせる染色からきているものが多い。同じ藍染でも、瓶覗から二藍、紺色とか。繊細にコントロールされていて、日本ならではの再現力と感性を表しているんですよね。表現の豊かさがずば抜けていて、洗練されている。田中一光さんとか感覚で選んだものであっても、そこに根付いている日本人ならではの色彩感覚を強く感じさせますよね。


流:瞳の色など、生物学的な条件も色彩の感覚に影響するのでしょうか。
周:科学的に検証されたデータはないと思いますので断定的なことは言えませんが、私は色の勉強とカラーマネジメントの仕事をアメリカでした経験から言うと、瞳の色は視覚に大きく影響するのだと考えられますね。それと育った環境も重要だと思いますね。どんな色に接してきたか、という。世界的に見ても、日本人は色に関する経験値が高いんじゃないかとは思います。
流:色に対しての感覚は後天的な影響もあるということですね。江戸時代の禁色の時に、市民が許されている色の中でも色を楽しんでいた四十八茶百鼠 からも日本人の色に対する工夫と繊細さが伺えますよね。例え話とはいえ、茶色と鼠色の中で48色と100色のグラデーションを感じるというエネルギーがあった、すごいです。色に対する情熱と繊細さを今も日本人は持っているはずなんですよね。
周:海外からお客様が来ると、私たちが見慣れているグレイッシュな壁一つとっても、「繊細なグレーがあるね」っておっしゃるんですよね。一つ一つの色の表現が繊細だと感じるようですね。
流:建築資材であってもものすごいバリエーションがありますよね。反対にヴィヴィッドな、気持ち良く突き抜けたような色がないのは不満ですが……。
周:東京は特に、彩度感が高い色の配色は取り入れにくい環境ではありますね。東京にいると白、黒、グレーの服を着てしまいますが、そのままイタリアに行くと、「あなた本当に色の仕事しているの?」と言われるんですよね(笑)。


日本の色を考えることは
日本を考えることでもある
流:今回このプロジェクトを立ち上げるにあたり、和田三造 が何を考えていたのか知るために改めて文献を読み漁ったんです。谷崎潤一郎と和田が鼎談している本でも「見ましたか、あの色!」というように興奮気味に語ったりしているのが戦後の日本に入ってきたアメリカの色で、センセーションだったようなんですね。この歴史的背景は発見でしたね。しかし、時間の経過とともに私たちはその色に対して単一で叙情がないことにつまらなさを感じていて、日本の色について改めて考え始めたのは面白い流れだなと思うんです。
中川:このプロジェクトを進めていて感じているのは、私にとって伝統色というものが自分の色に対して知識や感覚を形成したということです。学生時代にアメリカに留学していた時にも強く感じましたが、グラフィックの授業で提出する課題にも自然と日本を象徴する色を使いたくなってしまう。それは日本人としての矜持が色として出てたんだと思いますね。日の丸の紅だったり、障子や和紙のようなキナリ、白、金箔の金のような。それと、藍も重要ですよね。これらの色は自分もしかり、日本人である私たちの根底に根付いるんですよね。
流:伝統色は自ずと私たちにしっかり息づいていますよね。そして、たくさんの情報や価値観に触れらるようになった今、色においての多様性も考えていくべき時が来たようにも思います。
周:さまざまな職人に取材をしていて感じているのは、現代のクラフトマンシップからこそ新しい色は生まれるのではないかと。数百年の歴史を背負っている後継者である彼らは皆、伝統を活かしながら新しいものを作っていこうと意欲的なんですよね。彼たちが見ているのは東京ではなく、世界。世界の美術館でコレクションしてもらえるようなクリエイティブなものを作りたいと思っているんですよね。中川さんのような世界規模の発想やマインドをもっていて、そして技の技術もちゃんと持っている人たちが色の担い手なのではないでしょうか。
流:技術であったり表現を発信しようとする動きは確実に起こっていますよね。素晴らしい伝統的な文化があるゆえに、現代にアップデートされていないというのは、色だけでなく、、もしかしたら日本のあらゆることに言えることなのかなと思うんですよね。昔はあったはずのエネルギーが弱まっているような。アジア各国のエネルギー量が高いので、外から日本を見ている人で危機感を感じている人も多いです。一方で、伝統工芸だったりモノづくりをする個人がNYに出ていく姿もよく見かけるようになりました。技はあるから、サポートさえあればどんどん出ていけるんですよね。職業も暮らす場所も様々な方にインタビューしていると、色の話と共に「日本のあるべき姿」が見えてくるのではないかと思っています。このサイトが日本の見つめ直すきっかけになるといいかなと思います。